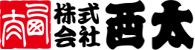気が付けば私も来年還暦を迎えることになりますが、初老の自覚がない…。いつそれに気が付くのかが楽しみでもあり不安でもある。きっと社員が、私が伝え続けた事を実行し、成果を出したところから初老に気が付くのではないかと思っております。
私は、その初老の自覚を持たないためにも、変革し続けたいと思います。まだまだ若いもんには負けないぞと。
昨年より、あまり営業に口を出さぬようにしていますが、目に余る事をしでかす。同じ失敗を繰り返す。ただ、少しずつその回数が減ってきていることも事実。
反省したらあとは飛躍のみ。
自分の目標を持つこと。これってこんな時代だから大事なことなんだよな。
緊急事態宣言があけて、勢いづいた11月!しかーし、その勢いも失速ぎみの12月のスタート。そんな悶々とした空気を一転させてくれたのが、第73代横綱 照ノ富士関。


![]()
地獄から這い上がって復活!そしてこの九州場所は全勝優勝!いう事なし!!このパワーを西太はキッチリいただきました(^^
忙しい中、お疲れのところご苦労様でした。横綱に負けぬよう西太も頑張ります!どすこい!!
SDGsの観点は、素晴らしいと思うのですが、気を付けないといけないと思っているのが、その解釈。日本国は島国。大陸の人種とはちょっと違う面がある。国勢がそれを物語っている。国勢がないから人付き合いやルールをDNAに組み込まれているかの如く、よく厳守する。他国から見れば不気味ともいうべき「大人しい国民」忍耐が身についている。
SDGsの観点から解釈を間違えると、人付き合いが疎遠になるというか「失礼なやつ」「常識知らず」などと言われる可能性も捨てきれない。国民に確実に浸透しない限り、何かモヤモヤ感が残る結果となる可能性がある。
国勢のない日本では、「国際的に言う無駄」が内需拡大にとって大事な事と思っています。何もかも国際的に合わせたがり、周りを意識しすぎる面がある。
国勢のない日本は、定住民族のDNAからくる面倒なくらいの人付き合いが必要と思います。人のために時間を費やすことも大事な「絆」。冠婚葬祭からはじまりお中元お歳暮そして年賀状など。
いずれ渋谷スクランブルは、ぶつかり合う人が増える日が来るんでしょうか。
コロナ禍で少し人間関係にも変化が出てきているようです。いい面と悪い面ありますが、仕事をするうえで人間関係を無視しては成立しません。
仕事をする上で「目配り 気配り 心配り」がとても重要。それは私のモットーとしている「人に優しく 仕事に厳しく」につながるからです。
目配り:仕事の完成度の確認です。取引先に失礼がないか、段取りよくいっているかを目視のみならず確認すること。
気配り:仕事、作業に無理・無駄・ムラがないかをチェック。自分の担当の仕事以外への配慮も。ちょっとした気配りで、仲間を助ける結果にもつながることもあります。
心配り:仕事をする人達への配慮。公私にわたり個人ではいろいろなことが起き、感情が不安定になることも多々あります。人間ですから。しかし、仕事に影響があってはならない。そんな時、お互いに心配りする思いやりがあれば悪化は避けられます。
何事も視野を広く持つことで、自分の立ち位置と周りの立ち位置が見え、自分の使命が見えてくるはずです。関わらない、自分さえよければは、いつか自分に跳ね返ってきます。
さあー気が付いたら前に向かって進みましょうー
仕事を任される重圧って結構ある。オリンピック見てても、数々の国内はもとより海外で多数の試合を経験してても、自国開催での不特定多数の人の底知れぬ期待の重圧を、選手を見て感じ取れる場面が多い。試合後の表情から見て取れる。
仕事もプロスポーツもよく似ていて、ともに生活がかかっていること。任された仕事を全うすることに、すべてをかける。それは、信用・信頼・期待・名誉と収入を得るために。
任された人は、周りから期待という視線で常にみられる。それに気が付いている人とそうではない人では、先行き大きな開きが出るのは言うまでもない。一方、任した人は、心のどこかで不安の二文字がチラつく。任せた人が、唯一なる安心できる事は、その仕事に起きるであろう問題を、いつでも解決できるという自信に他ならないであろう。その自信を手に入れるために、日夜努力をしなくては、手に入らない。それは、監督指導する上席の立場の使命。
自信がないは、いずれやる気が出なくなり、かと言って仕事もしなくては生活できなくなる。そうすると潜む社員となって、余計に目立たないような行動に徹するそうです。
私は、結果ではなく過程が大事であると思っています。過程とは、自分なりの目標・目的に向かって「どういう努力したのか」です。それをすすめるには、気配り・目配り・心配りが必要です。
そういった努力と経験が、いずれ「責任」ということも知らず知らずに身をもって知ることになり、更に責任には権限が付与され、責任と権限を有する上司となるのです。
先ずは、具体的に行動!
いろんなことがあっても、とうとうオリンピックが開催されました。報われた人、報われなかった人それぞれ複雑な気持ちでしょう。オリンピックを目指して日々自分の限界まで追い込んで、出場の切符を取ったアスリート達。一方で、パンデミック状態の日本において、お祭りごとやるなんてどうかしてると訴える人達。アスリート達も複雑な気持ちで今大会に臨んでいる。開催を反対している人も、一生懸命競技をしているアスリートを応援している。
誰のせいでもないけど、ここで運と努力が実ったアスリート。半強制的に開催を強いられた国民。運を手に入れたのだから、アスリートにはより一層頑張ってもらいたい。感染拡大に歯止めがきかなく、毎日犠牲になる人たち。その家族は、どんな心境でオリンピックを見ているのだろうか。きっと選手を応援していると信じたい。今回のオリンピックは、多くの犠牲を払っていることをアスリートは分かった上の、発言、行動でなくてはならないと思う。恒例のオリンピックとは違うという事を。
そもそも国民感情を逆なでするような、政治家の行動、組織委員会など、直接競技をする人ではない人が失態を繰り広げていて、オリンピックの価値観そのものと、何の罪もない人たちをきずつけているように思えてならない。
やった感だけを達成と勘違いをする人。今後は、あらゆる指摘を受けることだろう。
学校で教わった一番大事だった習慣って?一体何なんだろう。学校で教わることは、社会で役に立たないとかいう人がいます。私も役に立つのかな?と思っていました。それは、勉強の事ばかりに注目していて、習慣とか常識とかは家庭内に存在すると思っていたからです。実は学校では社会で役立つ大事な習慣を教えているのです。
それは「予習」「復習」「宿題」
これらは、すべて授業とは別な時間で行わなくてはなりません。スポーツ選手で自主トレなるものもソレ。勤務時間内に指示された作業をこなしているだけの仕事ぶりで、出世はもとより成功なんてありえないと思っているのは私だけでしょうか。努力したって成功するわけではないが、成功者は皆努力をしている。しかし、そういった人は自画自賛して「こんなに努力してる」というでしょう。勤務時間内は、発表の場です。それを成功させるには、予習復習が不可欠です。
努力というのは、予習復習と自分自身で課した宿題の事。
予習復習と自分自身で課した宿題を日々積み重ね、10年後の自分を想像してみよう。10年後の自分がどうなっているのかを。
3.11以来危機管理という言葉があまりにも日常になってしまい、ピンと感じ取れなくなってしまっているように思えます。更にコロナ禍において、つじつまの合わない日本政府のオリンピックへの対応、そんな国の対応から国民一人一人が、危機管理について、鈍感になってしまったように思えてなりません。
緊急事態宣言って本当に危機だから発令されるものなのに、オリンピックの招致を実行する。人を集めない集まらないようにしてくれと言いつつ、五千人収容とか1万人収容とかその次元の話をしている。緊急事態なんでしょ!そんな基本となる部分がファジーなために、言葉が軽くなり、政府に従うものがバカを見るような風潮になりつつある。
そんなレベルの危機管理を国がやってるもんだから、あちこちで緊急事態の意味が弱まり、法人・個人レベルでもファジージャッジになってしまい、正しい事の判断が出来なくなって、正しい判断をする人が悪に見えてまう。自分たちの都合だけで「ちょっとくらい」「切りのいいところで」など緊急を要する事が緊急にならず、私の嫌いな「できない理由」を探した結果のなにものでもない事に。
最悪の想定=危機管理が消えてしまっている。最悪の想定=危機管理こそ「どうすればこの難局をのりきれるのか」という前向きな考え方なのである。
何が起きるか分からないこの日本。まずは自分回りの最悪の想定=危機管理を見直すときではないでしょうか。
「その日の事は、その日のうちに」。生鮮は特に、同じ商品を毎日動かす、一瞬単純に思えるが、相場という日々動くものがあって、これがクセモノ。だから、毎日決算して一日の成果を知るのが望ましい。当然、それは営業レベルでの個人的、チーム的毎日決算。その日の締めの仕事。面倒だけれど、しなくてはならない。それが自分のスキルアップにもつながる。今日の反省と明日の目標、未来の目標ができる。それが毎日決算の意義。
誰でも嫌なこと、面倒なことなど、問題が起きると投げ出したくなるもんです。でも、それに携わっている仕事を担当しているからその問題が、自分に降りかかってくるのです。それは、自分に課せられた「責任」なのです。責任は、権限も有していますが、責任を放棄することは権限・立場も放棄することにつながることになります。
火は小さいうちに消さないと大火災になる。世界的な惨事でも、タバコ一本の火で何百ヘクタールも焼ける大火事になった例もあります。まさにソレと同じ。商売の場合は、取引が今後継続できるのかにつながる重要な問題に発展します。
明日を未来に向けて、前を向いていけるように、過去の案件で未来が台無しにならないように、毎日決算のクセを付けるようにしましょう!
このコロナ禍で、気力がフリーズしているようで、いつ解凍される日が来るのか自分でも不安になる。得意先の頑張り屋さんが、軽い鬱になったことで、益々不安になる。
周りを見渡すと淡々と作業をこなす社員がいて、作業終了すると蜘蛛の子を散らしたように消えていく。会社という法人は、それはそれでよい事と判断する。作業であればそれはそれでいい。
しかし、私は、仕事をするのと作業をするのとでは違うと思っていて、仕事がなければ当然作業が発生しない。暇という現在が、未来にデフレスパイラルにはまってしまったような妄想に囚われるんです。人は、時にこれを「小心者」とかいうでしょうね。まったりとした時間は、余暇ならいいのだけれど、仕事中もそんなムードに押し流されているような気がしてなりません。
さて、私は、このまったりムードを幾度もなく脱却しているんです。それは、「何事にもメリハリをつける」のです。そこで一番大切なことは「仕事をやらされてる感でやっているのか」「やってる感でやっているのかです」
それは、メリハリ行動のキーポイント。お金を度外視して、やっている感であれば、仕事がない事に不安をきっと感じるはずです。更にメリハリが出来ていると休みと仕事のケジメができていて、その結果その時その時に何が起きても自分自身が納得し、行動がとれるのです。
一方、やらされている感で仕事をしていると、当然指示のない役目的な仕事をスルーします。指示されても、やらされているという観念での行動なので、ミスも起きるし、完成度も到底悪い。当然評価はマイナス評価。チャレンジするなどの言葉は死語。
今、平等は24時間という時間とコロナ禍という状況で、できない理由を探して、言い訳するなどしやらないのではなく、どうすればできるのか、こんな暇はあってはならない、何かしなくてはならない、というポジティヴな思考を常に持ち、自分なりにメリハリをつける。そして、最後にどうやって笑顔を、一日の中で作るのかも忘れてはいけない。
仕事は8時間で終わるものではない。人生の3分の1以上仕事に時間を費やすのです。だからこそ、指示待ち妖怪にならないように、自ら仕事に対してやってる感とメリハリをもってやる。
いつの間にか私は、身についた。さあ~てと、休みましょ~。